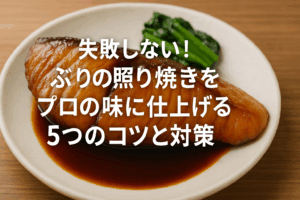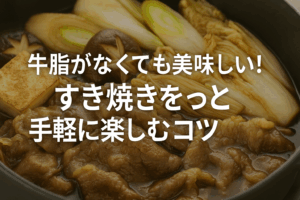「スープをもっと澄んだ仕上がりにしたいけれど、専用のこし器を持っていない…」そんなときってありませんか?
実は、どこのご家庭にもある キッチンペーパー があれば、手軽にスープや出汁を濾すことができるんです。
キッチンペーパーで濾すと、口当たりがなめらかになったり、見た目もきれいに仕上がったりと良いことがいっぱい。今回は、初心者の方でも失敗しにくい「キッチンペーパーでスープを濾すテクニック」を、やさしくご紹介しますね。
キッチンペーパーでスープを濾す魅力
キッチンペーパーを使う理由
ざるやこし布を用意しなくても、すぐに取り入れられるのが魅力。使い終わったらそのまま捨てられるので、洗い物を減らせるのも嬉しいポイントです。
他の濾し器との比較
- ざる → 手軽だが細かいアクや濁りは残りやすい
- 茶こし → 小さいのでスープ全体を濾すには不向き
- こし布 → 本格的だが洗うのが大変
その点、キッチンペーパーは「手軽さ」と「きれいな仕上がり」の両方を叶えてくれます。
デメリットと注意点
- 時間が少しかかる
- ペーパーが破れやすい
この2点を理解しておくと、よりスムーズに扱えます。
こんなときに便利!キッチンペーパー濾しの活用シーン
- 来客のとき、澄んだスープを出したいとき
- 洗い物を増やしたくない平日の夕食づくり
- 急いでいるときに簡単に濾したいとき
基本のスープ濾しテクニック
キッチンペーパーの種類と選び方
スープを濾すときは、普段のお掃除用や薄手のものではなく、調理用・厚手タイプ を選ぶと安心です。
- 厚手タイプ:濾す途中で破れにくく、油分や細かいカスもキャッチ。
- 無漂白タイプ:自然な色で安心感があり、紙独特のにおいも少なめ。
- エンボス加工タイプ:表面に凹凸があり、吸収力が強め。
💡もし迷ったら「リードクッキングペーパー」を選ぶと失敗しにくいです。
スープを濾す基本手順
- ボウルの上にざるをセット
ざるを下に置いてからキッチンペーパーをかぶせると安定して使えます。 - キッチンペーパーを敷く
少し湿らせてから敷くとフィットして破れにくいです。 - スープを少しずつ流し入れる
一気に流し込むと目詰まりや破れの原因になるので、お玉1杯ずつが目安。 - 自然に落ちるのを待つ
絞らずにそのまま自然に落とすと、澄んだスープになります。
スープの種類ごとの濾し方
中華スープ
油分が多いため、ペーパーを二重にすると透明度がアップ。
👉 濾した後に表面に浮いた油をスプーンですくうと、さらにあっさり仕上がります。
洋風ブイヨン
香味野菜や肉の旨みを残したいときは、粗めにざるで濾した後、仕上げにペーパーで濾す「二段階方式」がおすすめ。
和風だし
かつお節を濾すときは、途中でぎゅっと絞りたくなりますが、雑味が出やすいので自然に落とすのがコツ。
出汁を美味しく仕上げるコツ
- 強火で沸騰させない:アクや濁りが増えて、濾すのが大変になります。
- 常温〜少し冷ました状態で濾す:熱すぎるとペーパーが破れやすい。
- 二重濾しでプロ級に:一度濾したあと、別のペーパーで再度濾すと、料亭のように澄んだスープに。
ペーパーが破れないための工夫
- 湿らせる:乾いたままだと鍋やざるの形に沿わず破れやすい。
- 二重使い:特に油分や具材の細かいスープには必須。
- 流す位置を工夫:ペーパーの中央に集中的に注がず、左右にずらして注ぐと破れにくい。
キッチンペーパー活用の応用法
人気料理での使い方
カレー・シチューをなめらかに
- 仕上げ直前、火を止めてからお玉1杯ずつペーパーで濾すと口当たりがアップ。
- 具材の繊維が多いと目詰まりしやすいので、粗めにざる→ペーパーで仕上げの二段階がおすすめ。
鍋スープ(寄せ鍋・水炊き)をクリアに
- 食事の途中で濁ってきたら、お椀1杯分だけ取り出して濾し、鍋に戻すと全体が整います。
- 表面の油は、ペーパーをそっと表面に当てて吸わせるだけでもOK。
ラーメン・ポトフの脂を軽く
- スープを50〜60℃まで軽く冷ましてから濾すと、油が固まりはじめて分離しやすい。
- さらにすっきりさせたい時は冷蔵庫で一度冷やす→固まった脂を外す→仕上げに濾す。
茶碗蒸し・スープ卵
- 卵液を一度ペーパーで濾すと“す”が入りにくく、なめらか食感に。
お菓子づくりでの応用
プリン液
- 卵液と牛乳を合わせたら泡を立てないよう混ぜる。
- 温かいうちにペーパーで濾すと、ダマ・薄皮が除けて舌触りが格上げ。
カスタードクリーム
- もったり仕上がった後、熱いうちに濾す→急冷でダマ知らず。
- 目詰まりしたら新しいペーパーに交換して続行。
レアチーズ・水切りヨーグルト
- ボウル+ざる+ペーパーで冷蔵庫2〜3時間。
- 水切り後のホエイはスムージーやパン生地に再活用。
油分・アクのスマート除去
表面の油を“そっと”吸わせる
- スープ表面にペーパーを軽く触れさせて引き上げるだけ。混ぜないのがコツ。
香味油づくり(ねぎ油・ガーリックオイル)
- 香味野菜を油で弱火加熱→香りが立ったら火を止める。
- 完全に少し冷ましてからペーパーで濾すと、焦げの苦味が入らず澄んだ香味油に。
澄ましバター(簡易クラリフィエ)
- 溶かしバターを人肌程度まで冷ます→ペーパー濾しで乳固形分をカット。
- 本格的なギーほどは除去できませんが、ソテーやソースが軽い仕上がりになります。
「包んで煮出す」活用
自家製だしパック
- かつお節・昆布・煮干しをペーパーで包み、紐で軽く結ぶ。
- 煮出した後はパックごと引き上げられて後処理が簡単。
スパイス&ハーブのブーケ代用
- ローリエ・粒こしょう・クローブなどを包んで煮込みへ。
- 仕上げに取り出すだけで、雑味や粒の噛み当たりナシ。
※ 結ぶ紐は綿100%のキッチン用がおすすめ。金属クリップは鍋調理に使わないでください。
初心者でも失敗しにくい工夫
- ペーパーは軽く湿らせてセット:フィットして破れにくい。
- 量は“お玉1杯ずつ”:一気に注がない。
- 温度は熱々を避ける:50〜70℃程度まで落ち着かせると目詰まり・破れを防止。
- 二段階濾し:粗濾し→仕上げ濾しでスピードと透明度を両立。
- ざるを下に敷く:重さがかかっても安定し、破れのリスク減。
衛生&安全メモ
- 直火・オーブン不可(発火の恐れ)。電子レンジは短時間の保温程度に。
- 長時間の煮込みにペーパーを入れっぱなしにしない(繊維がほぐれるため)。
- 調理用の無香料・無着色タイプを選ぶと匂い移りを防げます。
- 衛生補足:使用済みのキッチンペーパーは再利用せず、調理後は必ず廃棄してください。濾したスープは清潔な容器に入れ、常温放置を避けて早めに冷蔵・冷凍保存を。
時短&効率化のアイデア
すぐ効く“基本の時短テク”
二段階濾しで最短クリア
- 粗濾し→仕上げ濾しの順にすると、目詰まりが激減して全体の時間が短くなります。
- 例:ざるだけで大きなカスを取る → キッチンペーパーで仕上げ。
温度帯を味方に(50〜70℃)
- 熱々はNG(破れやすく目詰まりしやすい)。
- ふうっと湯気が弱まる50〜70℃が落ちるのが早く、仕上がりも澄みやすいです。
面積を広げると流れが速い
- 大きめのざるや口径の広いボウルにセットすると、同じ量でも落ちが早い。
- 2台あれば並列で二面運用が最速です。
注ぐ位置を分散
- 中央一点に注ぐと穴が開きやすいので、左右へ少しずつ位置をずらして注ぎます。
ペーパーの事前セット
- 軽く湿らせて密着させ、二重に。
- 端を外側に折り返しておくと、取り外しが一瞬で済みます。
電子レンジで“濁りを減らす”下ごしらえ
肉・骨の下処理(例)
- くさみやタンパクの濁り源は、下処理で減らすと濾す量が少なくなって結果的に時短。
- 例:水をくぐらせた手羽元にふんわりラップ→600Wで2〜3分温め、出たドリップを捨ててから煮る。
香味野菜の下処理
- 玉ねぎ・人参・セロリはレンジで1〜2分加熱後に煮込みへ。灰汁が出にくく、澄みやすいスープに。
※ ラップはふんわり、やけどに注意。加熱直後は数十秒置いてから扱ってください。
並行処理&“濾しステーション”の作り方
セット例
- 鍋(注ぎ口側)→お玉→ざる+ペーパー→広口ボウルの直線配置。
- ボウルの下に濡れ布巾を敷いてズレ防止。
- 大量なら2レーン並行で投入待ちをゼロに。
リズム化のコツ
- お玉1杯注ぐ→30秒待つ→注ぐ位置を変えるを繰り返す。
- キッチンタイマーを30〜45秒に設定して流れ作業に。
目詰まり・破れ対策の“時短版”
1分ルール
- 1分以上ほとんど落ちない→潔く上のペーパーだけ交換。無理に待つより早いです。
油は先に吸わせる
- 表面の油はペーパーを軽く当てて引き上げてから本濾しへ。落ちが段違いに早くなります。
上澄みを先に濾す
- 鍋を少し傾け、澄んだ上層だけ先に濾す→最後に底の濁り部分を少量ずつ。合計時間を短縮。
時間別テンプレ段取り
5分で「そこそこ澄む」(〜1L)
- ざるで粗濾し→
- 50〜60℃まで冷ます→
- ペーパー1枚で周辺に注ぎ分ける。
10分で「プロっぽく」
- 粗濾し
- ペーパー二重で本濾し
- 仕上げに新しいペーパーで一杯だけ再濾しして透明感アップ。
大量(3L程度)の時
- 二面並列+上澄み先取り+途中で上の紙だけ交換。投入待ちを作らないのがコツ。
ペーパーの使い分けで時短
厚手 vs 薄手
- 厚手:破れにくく手数が減る(時短向き)。
- 薄手:二枚重ね→上の1枚だけ交換でコスパ&スピード両立。
使い捨てだしパック併用
- 具材(かつお節・スパイス)を最初からパックに入れて煮出せば、引き上げ一発で後処理が最短。
後片付けを最短化
ワンアクションで撤収
- ペーパーの四隅を外側に折っておく→端をつまんでスポッと外すだけ。
- ゴミはくるっと丸めて水分を落としてから捨てると、袋が汚れにくい。
シンク汚れ防止
- ざるの下にトレーを敷いて滴受け。作業台が汚れず拭き取りが一拭きで完了。
ミニQ&A(時短編)
Q. 急いでいるのに落ちない!
A. 温度を下げる→注ぐ位置を分散→上の紙を交換。この順で。
Q. 途中で紙が破けた…
A. ざるを下に敷いていれば被害は最小。紙を二重にして再開。
Q. さらに透明度を上げたいけど時間がない
A. 最後の1杯だけ新しい紙で再濾し。全量やり直すより速く効果的です。
スープ濾しにおすすめのキッチンペーパーランキング
人気商品の特徴と選ばれる理由
キッチンペーパーは種類が多く、どれを選んでよいか迷ってしまいますよね。ここでは、スープ濾しに向いている人気商品を紹介します。
- リード クッキングペーパー
調理専用に作られているので吸収力が高く、破れにくいのが特徴。スープ濾し初心者さんにも安心です。 - スコッティ ファイン
厚手でしっかりとした紙質。スープだけでなく揚げ物の油切りや野菜の水切りにも活用でき、万能感があります。 - キッチンタオル(無漂白タイプ)
自然派志向の方に人気。紙のにおいが気になる方や、小さなお子さんがいるご家庭におすすめです。 - 100均商品(ダイソー・セリアなど)
コスパ重視ならこちら。手軽に試せるので、「まずはやってみたい!」という方にぴったり。
価格帯別おすすめ
100均・低価格帯(お試しにぴったり)
- 1ロール100〜150円程度
- 初めて試す方や、一度きりの使用なら十分。
- ただし薄手のことが多いので、二重使いがおすすめです。
中価格帯(200〜300円前後)
- 吸水性・強度が安定していて、家庭料理で使うにはちょうどいいバランス。
- スーパーやドラッグストアで手に入りやすいのも魅力です。
高価格帯(300円以上)
- 厚手で破れにくく、仕上がりの澄み具合もワンランク上。
- 煮込み料理や来客用のきれいなスープを作りたいときに最適です。
買い方のコツと保管方法
買い方のコツ
- サイズを確認:大きめのざるやボウルに合うロールタイプがおすすめ。
- 厚みをチェック:厚手タイプなら破れにくく、濾す時間も短縮できます。
- まとめ買いもアリ:頻繁に料理をする方は、まとめて買うとコスパ良し。
保管方法
- 湿気が大敵!必ず乾燥した場所に置きましょう。
- キッチンに出しっぱなしにすると水蒸気でヨレてしまうことも。
- ケースや袋に入れて、立てて保管すると型崩れしにくいです。
💡まとめると…
- コスパで選ぶなら100均
- 安心感で選ぶならリード
- バランス派はスコッティ
それぞれの家庭スタイルに合わせて使い分けると、料理がもっと快適になりますよ。
濾したスープの美味しい保存法
保存容器の選び方と衛生面
せっかく丁寧に濾したスープは、清潔な容器に保存するのが基本です。
- ガラス容器(耐熱タイプ):匂い移りが少なく、温め直しもそのままできるので便利。
- 保存袋(ジップタイプ):冷凍保存におすすめ。平らにすれば場所を取らず、解凍もしやすいです。
- タッパー(プラスチック容器):手軽ですが、油分が染みつきやすいので短期保存向き。
👉 容器は使う前に熱湯やアルコールでサッと消毒しておくと安心です。
冷蔵保存のポイントと日持ち目安
濾したスープは雑味が少なく澄んでいる分、風味が落ちやすいのが特徴です。
- 冷蔵保存:2〜3日以内が目安
- 保存中は必ずフタをしっかり密閉して、他の食品の匂いが移らないようにしましょう。
- 冷蔵庫に入れる前に、常温まで冷ましてから保存すると結露を防ぎ、傷みにくくなります。
冷凍保存で味を落とさないコツ
「たくさん作ったから残ってしまった」というときは冷凍保存が便利です。
- 平らにして冷凍:保存袋に入れて薄く平らにすると、早く凍って解凍も簡単。
- 小分け冷凍:製氷皿やシリコンカップに入れて冷凍すると、少量ずつ使えて便利。
- 冷凍保存期間:およそ1か月が目安。
👉 解凍は冷蔵庫でゆっくり自然解凍するのがおすすめ。急ぐときは電子レンジの解凍モードでもOKです。
ダシやスープの使い切りテクニック
保存したスープを最後まで美味しく活用するアイデアもご紹介します。
- 炊き込みご飯に:スープで炊くだけで風味豊かに。
- 煮物の出汁に:薄味の煮物がぐっと美味しく。
- ソースやシチューのベースに:旨みが増してワンランク上の仕上がりに。
- 卵料理(茶碗蒸し・卵焼き)に:優しい旨みがプラスされます。
💡ポイントまとめ
- 短期保存なら冷蔵、長期なら冷凍。
- 清潔な容器を選ぶことが美味しさキープの秘訣。
- 保存したスープは「使い切る」工夫で、最後まで美味しく楽しめます。
よくある失敗と解決法(Q&A)
Q1. ペーパーが破れてしまった!どうすればいい?
A. ペーパーは熱々のスープや大量の油分で破れやすいんです。
- ざるを下に敷いておけば、スープが全部こぼれる心配はありません。
- 破れてしまったら、新しいペーパーを重ねて再スタートすれば大丈夫。
- 次回からは 二重にセットしたり、軽く湿らせてから使うと破れにくくなります。
Q2. スープがなかなか落ちない…時間がかかりすぎるときは?
A. 原因は「温度」と「油分」が多いことが多いです。
- 少し冷ましてから濾すと、落ちが早くなります。
- 表面の油は先にペーパーで軽く吸い取ってから濾すとスムーズ。
- それでも落ちないときは、上のペーパーだけ新しく交換してみましょう。
Q3. ペーパーの匂いが気になる…
A. 紙独特のにおいが気になる方は、以下を試してみてください。
- 無漂白タイプや調理専用のペーパーを選ぶ。
- 使う前に軽く水で湿らせてから使うと、においが和らぎます。
- 長時間スープに浸けっぱなしにしないことも大切です。
Q4. 油が多すぎて濾すのが大変!
A. 先に油をある程度取り除いてから濾すと楽になります。
- 表面に浮いた油をスプーンですくう
- ペーパーを軽く当てて油だけ吸わせる
このひと手間で、濾す作業がスピードアップします。
Q5. 澄んだスープにならないのはなぜ?
A. 濁りの原因は「強火で煮立てすぎ」「かき混ぜすぎ」などが多いです。
- 弱火〜中火でじっくり煮る
- できるだけ触らずにコトコト煮込む
- 仕上げに二段階濾し(ざる→ペーパー)をすれば、透明感がぐんと増します。
💡ワンポイント
「失敗かな?」と思っても、ちょっとした工夫でリカバリーできるのがキッチンペーパー濾しの良いところ。慣れてくれば自分なりのコツがつかめて、もっと手軽に美味しいスープが作れるようになりますよ。
まとめ|キッチンペーパーでスープをもっと手軽に
キッチンペーパーは、ちょっとした工夫で立派な「濾し器」になります。
専用の道具がなくても、スープや出汁をきれいに仕上げられるので、忙しい毎日のごはん作りにも大活躍してくれます。
今日のポイント
- 厚手や調理専用タイプを選ぶと破れにくい
- 二重にする・湿らせるなどのちょっとした工夫で失敗を防げる
- 粗濾し+仕上げ濾しの二段階方式なら、プロのような澄んだスープに
- 保存は 冷蔵なら2〜3日、冷凍なら1か月 が目安
- 冷凍は 小分けにしておくと使いやすい
応用も楽しんで
- カレーやシチューの仕上げに
- プリンやカスタードなどお菓子作りに
- 煮込み料理や鍋スープの油取りに
- 自家製だしパックの代用にも
💡 キッチンペーパーを上手に使えば、料理の仕上がりがぐっとワンランクアップします。
「面倒そう…」と思っていた方も、一度試せばその手軽さに驚くはず。
あなたのスープ作りが、もっと気楽で楽しい時間になりますように。