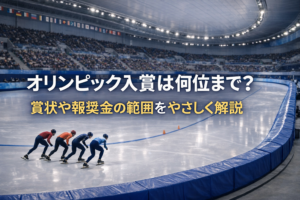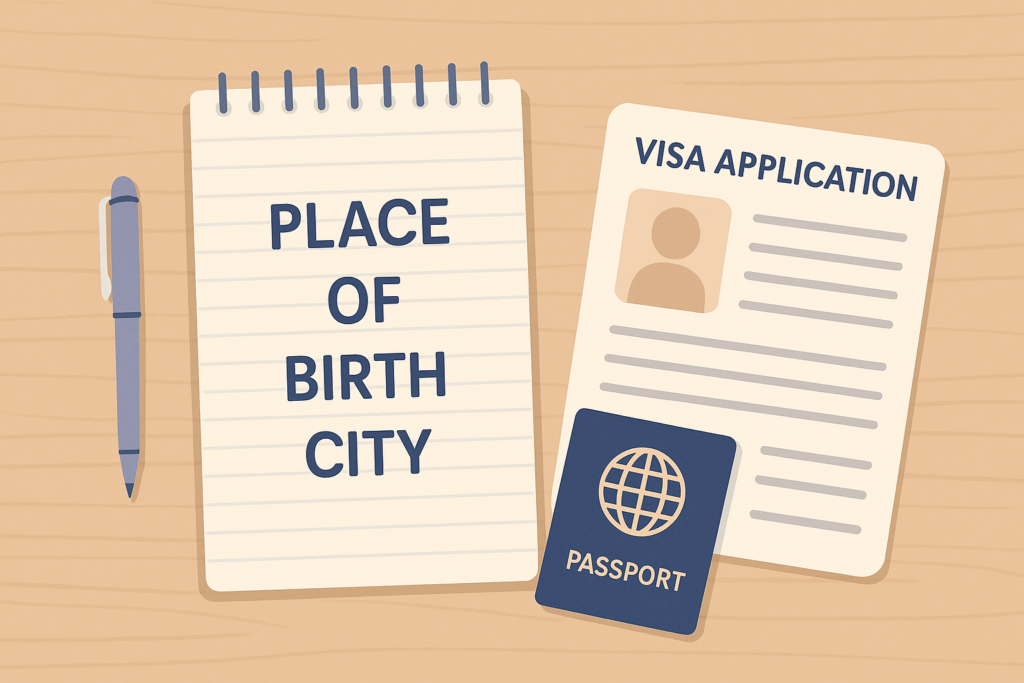
ビザの申請フォームを記入していると、英語で「Place of Birth City」という欄を見つけて「これ、どう書けばいいの?」と迷ったことはありませんか?
日本語でいう「出生地」ですが、国や申請書の形式によって書き方が少しずつ異なるため、思わぬミスにつながることもあります。
この記事では、「place of birth city」の正しい意味と書き方、よくある間違い、国別の注意点までを、やさしい言葉で解説します。
はじめてのビザ申請でも安心できるよう、例文やチェックリストもご紹介します。
「place of birth city」とは?|まず意味と基本を理解しよう
用語の整理:似ているけれど少しずつ違います
- place of birth:出生地(広い概念)。国・州・市など“どこで生まれたか”の総称。
- place of birth city:出生地のうち市区町村名を指す、“City(市)限定”の聞き方。
- country of birth:出生国(Japan など)。
- state/province of birth:出生州・県・省(米国の州、日本の都道府県などに相当)。
つまり「place of birth city」は、“生まれた市の名前だけを英語で書く欄”という理解でOKです。
どうして「city」だけ聞かれるの?
ビザ審査では、身元確認のために粒度(細かさ)を揃えたデータが必要です。国名は別欄で扱うことが多く、
市名だけを聞くことで、世界中の申請者の情報を同じ基準で比較・照合しやすくしています。
日本の住所となにが違うの?
日本の住所は「都道府県+市区町村+番地…」の順ですが、“city欄”では市区町村名のみを書きます。
- 例:東京都世田谷区で生まれた → Setagaya(Tokyo や Japan は別欄で指定されることが多い)
よくある誤解
- × Tokyo city / Tokyo-to / Setagaya-ku, Tokyo, Japan(盛り込み過ぎ)
- ○ Tokyo(23区内の区名より、東京生まれとして扱う指示があるケースが多い)/Setagaya(“区まで”を求める国・フォームの場合)
正解はフォームの指示に合わせます。“City(市名)を入れてください”と明記されていれば、市名(または区名等)まで。
“Place of Birth(自由記述)”なら「City, Country」の形を求められることがあります。
「市がない場所」で生まれたら?
日本では“町・村”もありますが、多くのフォームは city に一括しています。
- 町・村で生まれた場合:
- フリーテキスト欄 → Miharu(三春町 なら Miharu)。「-cho/-machi/-mura」は多くの国で不要。
- プルダウン(選択式) → 最寄りの市相当が候補にある場合はその指示に従う(ヘルプに案内があることも)。
海外で生まれた日本人の場合
- 例:米国・ロサンゼルスで出生 → Los Angeles(city欄)、United States(country欄)
- 里帰り出産などで出生国と国籍が異なることは珍しくありません。city と country を正しく分けて入力しましょう。
「出生病院の所在地」と混同しないコツ
出生病院の住所と“行政上の市名”がずれることがあります。出生証明書の市名を優先し、
迷ったらパスポート申請時に使用した表記(または戸籍の記載と整合)に合わせるのが安心です。
英語表記の基本ルール(小さなつまずきを回避)
- ローマ字は先頭大文字+残り小文字:Osaka, Kyoto, Fukuoka
- 接尾語は基本つけない:Kyoto-shi → Kyoto、Hokkaido-ken → Hokkaido(※“city欄”は市名に限定)
- 長音や小書きは簡潔に:Ō → O(HeBon式に準拠。Tōkyō → Tokyo)
- 国名や都道府県名は重複させない:City欄に Japan や -to/-ken は不要
ミニ表:代表例
- 札幌市 → Sapporo
- 名古屋市 → Nagoya
- 横浜市 → Yokohama
- 北九州市 → Kitakyushu
- さいたま市 → Saitama
※ 区名の指定がない限りは、政令指定都市は“市名のみ”が無難です(例:Sapporo、Yokohama など)。
合併・改称があったときの考え方
- 原則:出生当時の市名で問題ないことが多い
- ただし、フォームが“現行の地名”を求める場合もあります
- 自由記述欄があれば、“旧〇〇(現〇〇市)”のように補足すると丁寧
最終的にはその国のフォーム指示が最優先。迷ったら問い合わせ(後掲テンプレ)で確認しましょう。
例で理解:ありがちな3パターン
- 東京23区で出生
- 指示が「City only」→ Tokyo
- 指示が「City/District」→ Shinjuku など区名を許容する場合も
- 町・村で出生
- テキスト欄 → Kumejima(久米島)
- 選択式 → 該当がなければガイダンスに従い最寄りの市等
- 海外で出生
- City:Honolulu / Country:United States
困ったときのミニFAQ(第1章版)
- Q. City欄に「Japan」は必要?
A. 不要です。国名は別欄(Country)に入力します。 - Q. “Tokyo city”はダメ?
A. 多くのフォームで冗長なので Tokyo が無難。 - Q. 区名・郡名まで必要?
A. 指示がない限り市名レベルで十分。指定があれば従う。 - Q. ローマ字は長音付き(Tōkyō)にする?
A. 一般に Tokyo と簡略表記します(ヘボン式)。
提出前ミニチェック
- 市名だけを書いている(県名・国名を足していない)
- 大文字・小文字が適切(Sapporo / Nagoya / Kyoto)
- 出生証明・戸籍・パスポート申請時の表記と矛盾がない
- 合併や改称がある場合、フォーム指示に合わせている
- 迷った点は公式窓口に質問済み(任意)
ひとことアドバイス
最初は「英語で地名を書くだけなのに…」と不安になりますよね。
でも大丈夫。“市名だけ、シンプルに、パスポート等と一致”が基本ルール。
ここさえ押さえれば、あとのステップはぐっと楽になります。
ビザ申請での「place of birth city」の重要性
なぜ「city」の正確な記入が大切なの?
ビザ申請では、申請者の身元を国際的に特定することが最も重要です。
出生地の情報は、パスポートや戸籍、過去の入国履歴などと照合されるため、
ここで誤りがあると「別人」と判断されるリスクがあります。
特に最近は、オンライン申請の自動照合システムが主流です。
そのため、人間の目よりも正確な一致が求められる傾向にあります。
一文字違うだけでも「同一人物か確認できません」とされ、再提出になるケースも。
小さなミスが、申請全体の遅れにつながることもあるのです。
「place of birth city」はなぜ“身元証明”になるの?
出生地は「その人が最初に公的記録に載る場所」。
パスポートや出生証明書など、すべての身分証明書の“起点”となる情報です。
具体的にどう使われているの?
- パスポート申請情報との照合
→ ビザセンターは、申請内容とパスポート・戸籍情報を自動的に突き合わせます。 - 過去の渡航履歴データとの照合
→ 以前の申請と異なる地名が登録されると、「データ不一致」と判断されることも。 - 国籍や出生国の確認
→ 出生地が海外で国籍が日本の場合など、特に慎重に審査されます。
記入ミスが与える影響
軽微なミスであっても、確認に時間がかかる
- 「Tokyo-to」と入力 → システム上は「Tokyo」と一致せず、再確認対象に。
- 「Kyoto, Japan」と書いた → 「Japan」が重複扱いになり、修正依頼が来ることも。
審査官が混乱する例
- 書類A:「Kyoto」
- 書類B:「Kyoto-shi」
このように表記が微妙に異なるだけで、別の市として扱われることがあります。
トラブル事例
- オンライン申請で「Shizuoka city」と入力したが、
→ システムには「Shizuoka」しか登録されておらず照合エラー。 - 旧市名(例:伊都郡高野口町)を記入したら、
→ 現在の地名「橋本市」として書き直すよう求められた。
国ごとに“重視度”が違うことも
アメリカ(ESTA・DS-160など)
非常に厳密に照合されるため、市名のみ(City)を正確に英語で書く必要があります。
長音や小文字の違いも認識される場合があり、入力時の注意が必要です。
オーストラリア・カナダ
こちらは柔軟性があり、「Place of Birth(City, Country)」のように
国名を含めて書く形式も見られます。
ただし、国名が別欄にある場合は重複しないようにしましょう。
欧州圏のオンラインフォーム
ヨーロッパの一部では、自動入力候補(City一覧)から選ぶ方式。
該当する市が見つからない場合は「Other」や「Unknown」を一時的に選べるケースもあります。
審査官がチェックする主なポイント
① 国籍情報との一致
パスポートの国籍情報(Nationality)と出生地の国(Country of Birth)が矛盾していないか。
② 出生証明書との整合性
海外出生者・二重国籍の方は、出生証明書上の表記がそのまま使われます。
ここが一致していないと、追加証明書(Birth Certificate)の提出を求められる場合も。
③ 過去申請データとの一致
ビザは1回きりではありません。
前回申請時の「Place of Birth City」と異なる表記(例:Osaka → Osaka-shi)になっていると、
再確認の対象になることがあります。
間違いを防ぐコツ
1. パスポート申請時の資料を確認
戸籍抄本や出生届など、最初に使った表記に合わせるのが一番安全です。
2. 各国の公式ガイドを確認
ビザセンターや大使館のFAQに、
「Place of Birth City の書き方」や「よくある間違い」が掲載されていることがあります。
3. 不安なときは問い合わせる
英語での問い合わせが不安な場合は、以下のようにシンプルに聞きましょう。
I would like to confirm the correct format for the “Place of Birth City” field.
(「place of birth city」欄の正しい書き方を確認したいです。)
まとめ:記入は“正確さ”が最優先
「たった一行の英語」でも、ビザの審査では重要な身元情報になります。
焦らず、パスポートと出生証明に合わせて正確に記入することが、
スムーズな審査への第一歩です。
コツは「シンプルに・一貫して・公式基準に沿って」。
迷ったら、都道府県や国名を省いて“市名だけ”を英語で書くのが基本です。
正しい「place of birth city」の書き方
まず押さえておきたい基本ルール
「place of birth city」の欄には、“生まれた市区町村の名前を英語で”書きます。
日本の場合は「都道府県」や「国名(Japan)」を足す必要はありません。
✅ 基本の形:市名だけを英語で
例)東京で生まれた → Tokyo
大阪で生まれた → Osaka
札幌で生まれた → Sapporo
注意点
- 都道府県名(Tokyo-to, Osaka-fuなど)は不要。
- “City”や“Japan”をつけるのも避ける。
→ “Tokyo city”や“Tokyo, Japan”は誤りになりやすい。 - 略称やスラングはNG。(例:“Kyoto-shi”ではなく“Kyoto”)
英語表記で迷わないためのコツ
ヘボン式ローマ字表記を使う
日本人の名前や地名は、外務省が定める「ヘボン式ローマ字」に合わせて書くのが原則です。
特にパスポート・ビザ・航空券などで表記が統一されるため、
長音や小書き文字を省略した形で書くと良いでしょう。
| 日本語表記 | 英語表記(推奨) | よくある間違い |
|---|---|---|
| 東京 | Tokyo | Tōkyō(長音付き) |
| 京都 | Kyoto | Kyouto |
| 名古屋 | Nagoya | Nagoya city |
| 福岡 | Fukuoka | Fukuoka-ken |
| 札幌 | Sapporo | Sappro(誤り) |
ポイント: 英語表記では「長音符号」や「-shi/-ken/-fu」は省き、
シンプルな綴りにするのが国際的な標準です。
都道府県や国名はいつ書くべき?
1. 「City」欄がある場合
→ 市名のみを記入(例:Kyoto)
都道府県や国名は別の欄にあるため、重複は避けましょう。
2. 「Place of Birth」だけがある場合
→ 市名+国名で書く
例)Osaka, Japan / Kyoto, Japan
このように「市+国」の形にしておくとわかりやすく、審査でも混乱しません。
3. 「自動入力フォーム」の場合
候補に自分の出生地がないときは、最寄りの市を選択したうえで、備考欄に「Born in ○○ town」などと補足すると丁寧です。
市がない場合・合併で名称が変わった場合
町や村で生まれたとき
「City」という言葉にこだわらず、正式な町名や村名を英語表記で書いて構いません。
例)三春町 → Miharu / 白馬村 → Hakuba
市町村合併で地名が変わったとき
基本は出生当時の地名を使います。
ただし、フォームに「現行の市名を記入」とある場合は新しい名前で記入します。
例)旧「高野口町」で出生 → 現「橋本市」なら “Hashimoto” と記入。
迷ったときは「旧○○(現○○)」と補足するのもOKです。
旧字体や特殊な地名の扱い
「栃木」や「埼玉」など、読みが難しい地名は標準のローマ字表記で記入します。
英語に直訳するのではなく、発音に近い綴りを使いましょう。
| 地名 | 英語表記 | 補足 |
|---|---|---|
| 仙台 | Sendai | 長音なし |
| 奈良 | Nara | 短い綴りでOK |
| 鹿児島 | Kagoshima | Japanは不要 |
| 那覇 | Naha | okinawa cityではない |
オンライン申請での入力例
例:アメリカビザ(DS-160)
- City of Birth:Tokyo
- Country/Region of Birth:Japan
→ 両方の欄があるため、市名だけでOK。
例:オーストラリアETA
- Place of Birth:Osaka, Japan
→ 1つの欄しかないため、「市+国」で記入。
例:ヨーロッパのETIAS
- 自動候補リストから選ぶ形式。
→ “Kyoto”や“Sapporo”など候補に一致するものを選択。
ミスを防ぐためのチェックポイント
チェック1:過剰な情報を書かない
→ “Tokyo city Japan”のように複数要素を入れると照合エラーになります。
チェック2:小文字・大文字の統一
→ 頭文字だけ大文字(例:Osaka)
チェック3:出生証明・パスポートと一致
→ 以前の書類と異なる綴りになっていないか確認。
チェック4:旧市名・町村名を誤記していない
→ 変更がある場合は公式サイトで現地名を確認。
よくある質問(Q&A)
Q. 「Tokyo-to」「Osaka-fu」などはダメですか?
→ はい、不要です。英語では「Tokyo」「Osaka」だけで十分です。
Q. 長音(ー)はどう書くのが正しい?
→ ヘボン式では「Tokyo」「Fukuoka」のように長音を省略します。
Q. 小さな町に生まれた場合はどうすれば?
→ 「Miharu」など、正式なローマ字表記でそのまま書いて問題ありません。
Q. 生まれた市が存在しない(合併された)場合は?
→ 現在の市名で書くか、「旧○○(現○○)」と備考に補足しましょう。
最後に|「迷ったらシンプルに」が正解
「place of birth city」は、たくさん情報を書こうとするほど間違いが増えます。
英語の書き方に自信がなくても、“市名だけ・ローマ字で・公式に合わせて”と覚えておけば大丈夫です。
書類全体で大切なのは“統一感”。
パスポート・申請書・証明書のすべてで同じ表記にしておくと、審査もスムーズに通ります。
国別・申請方式別の記入の違い
国によって「place of birth city」の書き方は違う?
同じ「ビザ申請」でも、国によって申請フォームの書き方やチェックの仕方が少しずつ異なります。
中身はほぼ同じ意味でも、「どこまで書くか」「どんな形式で書くか」が違うだけで、記入ルールは変わってくるのです。
ここでは、主要な申請国(アメリカ・カナダ・オーストラリア・ヨーロッパ)を中心に、それぞれの違いと注意点を見ていきましょう。
アメリカ(ESTA・DS-160)の場合
アメリカのビザ申請(観光・就労どちらも)は、最も入力形式が明確です。
フォームには 「City of Birth」 の欄があり、“市名だけ” を書くよう求められます。
記入例
- City of Birth:Tokyo
- Country of Birth:Japan
ポイント
- 「City」だけなので、都道府県名(Tokyo-to)は不要。
- 「Tokyo city」や「Tokyo, Japan」と書くと、重複扱いになることがあります。
- 長音符号(Tōkyō)など特殊文字も不要。TokyoでOKです。
アメリカのビザは電子審査が非常に厳密。
申請内容と過去のデータが1文字でも違うと「確認中(Administrative Processing)」になる場合もあります。
迷ったら、パスポートの表記に合わせるのが最も安全です。
カナダ(eTA・ビザ申請フォーム)の場合
カナダのオンライン申請では、「Place of Birth」とだけ書かれたケースが多く、
その場合は 「市名+国名」 の両方を入れるのが一般的です。
記入例
- Place of Birth:Osaka, Japan
ポイント
- 「City」欄がないときは「市+国」をセットで。
- 「Osaka only」だと、出生国が判断できない場合があります。
- 都道府県名(Osaka-fu)は不要です。
カナダの審査は比較的柔軟ですが、書類同士の整合性は重視されます。
パスポートのデータページに合わせるように統一しましょう。
オーストラリア(ETA・ビザ)の場合
オーストラリアもカナダと同じく、「Place of Birth」として一括入力する方式が多いです。
ここでも 「市名+国名」 のセットが推奨されています。
記入例
- Place of Birth:Nagoya, Japan
注意点
- 「city」「country」の別欄がない場合は、必ず両方書きます。
- 町や村の場合でも「Miharu, Japan」などでOKです。
- ローマ字の表記に不安があるときは、外務省のローマ字ガイドを参考にしましょう。
オーストラリアは、申請者が多い分システムの自動照合が多用されています。
フォーム上のコンマ(,)やスペースの位置まで丁寧に確認しておきましょう。
ヨーロッパ(シェンゲンビザ・ETIASなど)の場合
ヨーロッパのオンライン申請では、自動入力(プルダウン式)が多く、
登録されている都市名を選ぶ形式になっています。
記入例(プルダウン式)
- City of Birth:ドロップダウンから “Kyoto” を選択
- Country of Birth:Japan
記入例(手入力式)
- Place of Birth:Sapporo, Japan
注意点
- 自分の出生地がリストにない場合、「Other」や「Unknown」を選ぶ選択肢もあります。
- 備考欄がある場合は、「Born in ○○ Town (Japan)」と補足してもOK。
- 「ü」「ö」など特殊文字は使わず、英語表記で入力します。
ETIASなどのEU共通システムでは、データ照合が機械的に行われます。
正式な都市名を選び、略称を使わないよう注意しましょう。
紙申請とオンライン申請の違い
紙申請
- 自由に書けるため、正式名称と整合性を重視。
- 「旧市名」「町・村」なども補足がしやすい。
- 手書きの場合は、綴りやスペルミスに注意。
オンライン申請
- 入力欄が限られており、「自動候補」や「選択形式」になる場合が多い。
- 候補にない場合、「Other」を選んで後で説明することも可能。
- 英語表記が間違っていると照合エラーが起きやすい。
入力欄に市名がない・候補が出ない場合の対処法
- 最寄りの大都市を入力(例:Kumano町 → Shinguなど)
- 備考欄があれば補足する
→ Born in Kumano Town, Japan - FAQやヘルプを確認する
→ “If your city of birth does not appear, please select the nearest city.” などの指示があることが多い。 - それでも不安なら問い合わせる
→ 以下のように質問するとスムーズです。
“My city of birth is not listed in the form. Which option should I select?”
(出生地が候補にない場合、どれを選べばよいですか?)
参考:英語変換に便利なツール
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Google翻訳 | 読みをローマ字変換する際に便利。ただし正式名とは限らないので注意。 |
| 外務省「ヘボン式ローマ字表記」一覧 | パスポート基準の表記を確認できる公式ガイド。 |
| Japan Post Romanization Tool | 郵便局の住所変換。市町村レベルの英語表記チェックに役立つ。 |
まとめ:国の指示に合わせるのが最優先
国によって記入ルールは少しずつ違っても、基本の考え方は同じです。
「生まれた市を英語で正確に」「過剰に書かない」――これが共通ルール。
迷ったときは、
- フォームに書かれている指示文(例:City only、Place of Birth)をよく読む
- 公式FAQを確認する
- 不明点はメールで問い合わせる
この3ステップを心がければ安心です。
国ごとに細かい違いはありますが、基本のルールさえ守れば大丈夫。
無理に完璧を目指すより、「整合性」と「統一感」を大切にしましょう。
地方名の表示方法とその影響
市町村合併・旧地名はどう扱えばいいの?
ビザ申請では、「現在の市名」と「出生当時の市名」が異なるケースもあります。
たとえば、かつて「高野口町(こうやぐちちょう)」で生まれた人が、
今は「橋本市」に統合されている――というような場合ですね。
どちらを書けばいいのか迷いやすいですが、基本は以下のように考えます。
✅ 原則は、出生当時の市名でOK。
ただし、フォームが「現在の地名で入力」と明記している場合は、それに従いましょう。
出生当時の地名で書く場合
記入例
- Place of Birth City:Koyaguchi(旧:高野口町)
- 備考欄に補足:Now part of Hashimoto City, Japan
このように、旧市名を書いたあとに現在の市名をカッコ付きで補足しておくと、
審査官にもわかりやすく、誤解を防げます。
現在の地名で書く場合
記入例
- Place of Birth City:Hashimoto(現行の市名)
申請フォームが「現在の行政地名に合わせるように」と明記している場合は、
出生当時の地名をあえて使うと照合がズレてしまうことがあります。
この場合は、現行の市名のみで統一して構いません。
公式サイトやフォームの「Help」欄に “Current name of the city” と書かれているときは、
現在の名称を優先しましょう。
略称・旧称・愛称を使うのはNG
「地元では通じるけれど、正式名ではない」表記は避けましょう。
たとえば──
| 誤りやすい表記 | 正しい書き方 |
|---|---|
| “Hiro” | Hiroshima |
| “Sapporo City” | Sapporo |
| “Kita” | Kitakyushu |
| “Yoko” | Yokohama |
「place of birth city」は公式文書として扱われます。
省略形や愛称を使うと、審査官が一致を確認できない場合があります。
「郡」「区」「町」「村」はどう書く?
郡の場合
郡は英語で “District” や “County” と訳されますが、
多くの国では省略して「町または市」で記入します。
例:上益城郡益城町 → Mashiki(郡名は不要)
区の場合
政令指定都市の「区」は、フォームで特に求められない限り省略可能です。
- 例:大阪市北区 → Osaka(City単位でOK)
- 「City/District」など明記されている場合のみ Kita-ku と記入します。
町・村の場合
町(Town)や村(Village)に生まれた方も、そのままローマ字表記でOKです。
例:
- 三春町 → Miharu
- 白馬村 → Hakuba
“Town”や“Village”を付けても構いませんが、省略しても問題ありません。
“Miharu Town” “Hakuba” のどちらでも受理されるケースが多いです。
地名が外国語由来・特殊文字を含む場合
一部の地域(例:稚内、会津若松など)は、英語にしたときの綴りが少し独特です。
日本語読みをそのままローマ字化し、特殊記号や長音を省いて書きましょう。
| 日本語 | 英語表記例 |
|---|---|
| 稚内 | Wakkanai |
| 会津若松 | Aizuwakamatsu |
| 宇都宮 | Utsunomiya |
| 鹿児島 | Kagoshima |
英語翻訳を意識するより、「パスポートに近いローマ字表記」に合わせるほうが安全です。
外国語風の綴り(例:“Aidu”など)は使わないようにしましょう。
旧市名→現市名対応の考え方
| 状況 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|
| 合併前の市名を記入 | “Koyaguchi (now part of Hashimoto)” | 出生当時の地名でOK |
| 現在の市名を優先 | “Hashimoto” | フォームが「現在の地名」と指定している場合 |
| 市が存在しない(郡のみ) | “Mashiki” | 郡名は省略 |
| 外国で出生 | “Honolulu” | Country欄に「United States」を記入 |
どちらを選ぶ場合も、一貫性(consistency)を大切に。
他の書類(パスポートや過去のビザ)と同じ表記にしておきましょう。
略称や旧名を使うと起こりやすいトラブル
- 照合システムで一致しない
- 「地名が存在しない」とエラー表示される
- 再提出を求められ、審査が遅れる
- 現地の審査官が判断できず問い合わせが発生
英語表記に自信がなくても、正式名称をそのままローマ字にするだけで十分です。
無理に翻訳しようとしないことが、最も安全な方法です。
まとめ:迷ったら“今の市名”か“出生時の正式名”で
合併や名称変更がある地域では、どちらが正しいか迷いやすいですが、
- 出生時の地名がはっきりしているなら、そのまま
- フォームが「現地名」と指定しているなら、最新の名称で
というシンプルな判断で大丈夫です。
一番大切なのは、他の書類との整合性と一貫性。
「昔の名前でも、今の名前でも、どちらも正式であれば間違いではありません。」
よくある誤解と間違い事例
「city」欄の書き方を間違えるとどうなるの?
「たった一単語の英語なのに、どうしてそんなに重要なの?」
──と思う方も多いですが、実はこの欄を間違えるとシステム照合の不一致が起こり、
申請全体が保留や再確認になるケースがあります。
誤記入そのものが“落とされる理由”にはなりにくいものの、
審査の遅延や追加問い合わせの原因になることがあるのです。
よくある間違い①:「Japan」や「prefecture」を重複して書く
例
- × Tokyo, Japan(City欄に国名まで記入)
- × Osaka Prefecture(都道府県名まで入れてしまう)
City欄はあくまで“市”の名前だけを記入する場所。
国名は別欄にあるので、ここに重複して書くとデータベース上で「別の地名」と扱われることがあります。
✅ 正しい書き方:
Tokyo / Osaka / Fukuoka など、市名だけでOKです。
よくある間違い②:「City」を単語ごと入力してしまう
例
- × Tokyo city
- × Sapporo city
日本語の感覚で「市」を付けてしまう方が多いですが、
英語では「city」という単語そのものが「都市名」を意味するため、重複表現になります。
✅ 正しい書き方:
Tokyo / Sapporo(“city”は不要)
よくある間違い③:長音・表記ブレによる不一致
日本語の長音「ー」や小書き文字(ゃ・ゅ・ょ)は、英語では省略されるのが基本です。
しかし、自己判断で別の表記を使うと、過去の記録と一致しなくなる場合があります。
例
- × Tōkyō(長音符号付き)
- × Fukuōka(長音をOで表現)
- × Kyouto(日本式ローマ字)
✅ 正しい書き方:
Tokyo / Fukuoka / Kyoto(すべてヘボン式)
ポイント:外務省が採用する「ヘボン式ローマ字表記」に合わせるのが安心。
「ローマ字変換」ではなく「公式表記」を選ぶ意識が大切です。
よくある間違い④:出生地が外国なのに国名を省略
海外で生まれた日本人の方の場合、「City」と「Country」欄の両方に記入が必要です。
ところが、国名を省略してしまうケースがよく見られます。
例
- × Los Angeles(City欄にだけ入力してCountryを空欄)
✅ 正しい書き方:
City:Los Angeles
Country:United States
※国籍(Nationality)が「Japan」でも、出生国(Country of Birth)は別情報として扱われます。
ここが一致していないと、再確認を求められることがあります。
よくある間違い⑤:旧市名や町名のまま入力してエラーになる
合併後に地名が変更された地域では、旧名のままだとフォームで認識されない場合があります。
例
- × Koyaguchi(旧市名・候補に存在しない)
この場合は、現在の市名「Hashimoto」などに合わせて書くか、
備考欄があれば「Born in former Koyaguchi Town」と補足しておきましょう。
よくある間違い⑥:日本語やカタカナをそのまま入力
フォームが英語で作成されている場合、日本語やカタカナ入力は認識されません。
例
- × 札幌(日本語)
- × サッポロ(カタカナ)
✅ 正しい書き方:
Sapporo(英語・半角アルファベットで)
よくある間違い⑦:区名・郡名を追加しすぎる
特に東京都などの大都市では、「区」を入れたくなりますが、
フォームの指示に「District」や「Ward」がない場合は省略しましょう。
例
- × Shinjuku-ku Tokyo(区名まで入れた)
- × Setagaya-ku(City only欄に区名)
✅ 正しい書き方:
Tokyo(区名は省略)
ただし、“City/District”と書かれた欄では「Shinjuku」や「Setagaya」でも可。
トラブル実例:申請が保留になったケース
事例①:スペルミス
City of Birth:Sappro → 正しくは Sapporo
→ 照合できず、再提出を求められた。
事例②:旧市名のまま記入
Place of Birth:Koyaguchi(現在はHashimoto)
→ 「該当地名なし」と判定され、再入力を指示された。
事例③:「city」を付けて入力
Tokyo city
→ システム上で“Tokyo”とは別の地名扱いになり、
自動照合に失敗。追加確認が必要になった。
正しい書き方を確認するチェックリスト
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 都道府県名・国名を省いている | City欄には市名だけ |
| 「City」単語を付けていない | “Tokyo city”はNG |
| スペル・大文字小文字が正しい | Osaka/Fukuoka/Nagoya |
| 長音を省いている | “Tōkyō”ではなく“Tokyo” |
| 旧市名や略称を使っていない | 現在の正式名称で統一 |
| 出生地が外国なら国名も記入 | City+Countryで一致 |
書いたあとにこの表をチェックするだけで、ほとんどのミスは防げます。
特に「重複」「旧地名」「スペルミス」は審査遅延の原因になりやすいので注意しましょう。
まとめ:「シンプル・統一・公式に合わせる」が合言葉
「place of birth city」は、思っているより“正確さ”が求められる項目です。
ただ、難しく考えすぎず、「パスポートや公式書類と同じ書き方」にそろえることが大切です。
● シンプルに:余分な情報を入れない
● 統一して:すべての書類で同じ表記にする
● 公式に合わせて:外務省や大使館の指示を参考にする
この3つを守れば、安心して申請書を提出できます。
トラブルを防ぐためのチェックリスト
記入前に意識したいこと
「place of birth city」はほんの一行の記入欄ですが、
申請システム上では本人確認の重要データとして扱われます。
うっかりした表記ブレや誤入力が、思わぬ審査の遅れにつながることも。
そこでここでは、実際の申請前に確認すべきポイントを
わかりやすいチェックリストにまとめました。
提出前に確認したい5つのポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| ① 市名だけを書いている | 都道府県名や「Japan」を重複して書いていないか |
| ② スペル・大文字小文字が正しい | “Tokyo”“Osaka”“Nagoya”などの綴りを再確認 |
| ③ パスポートと一致している | 過去の申請や書類と同じ表記にそろえる |
| ④ 現行の地名に合わせている | 合併・旧市名の場合は最新の地名か出生時の地名かを統一 |
| ⑤ 英語表記が公式基準に沿っている | 外務省ヘボン式ローマ字に合わせているか |
チェックのコツ
“英語で書く”よりも“他の書類と同じにする”という視点が大切。
ビザ申請の照合は、自動的に過去データと比較されることが多いため、
一貫性(consistency) が最も重視されます。
よくあるトラブル別の対処法
1. 入力後にミスに気づいた場合
- まだ送信前 → 修正して再確認すればOK。
- 送信後 → 多くの国では「修正リクエスト(amendment)」や「再申請」が可能です。
→ 公式FAQやメールで確認し、丁寧に説明しましょう。
2. 候補に自分の市が出てこない場合
- プルダウン形式なら、最寄りの市を選ぶ。
- 自由入力欄があるなら、「Born in ○○ Town, Japan」と補足します。
3. 旧市名を使ってエラーになった場合
- 現在の市名で再入力し、
備考欄や問い合わせで「旧名○○に出生」と説明すればOKです。
4. 英語表記に迷った場合
- 外務省「ヘボン式ローマ字一覧」か
日本郵便の英語住所検索ツールで確認します。
英語で問い合わせるときの例文テンプレート
件名: Question about “Place of Birth City” field
本文:
Dear Sir/Madam,
I would like to confirm the correct format for the “Place of Birth City” field in the visa application form.
My birth city is [例:Miharu Town, Fukushima].
Should I enter the current city name or the original one?
Thank you for your assistance.
Best regards,
[あなたの名前]
(日本語訳)
「place of birth city」欄の正しい記入形式を確認したいです。
出生地は[例:福島県三春町]です。現在の市名で記入すべきか、出生当時の地名でよいか教えてください。
※英語が不安な場合は、文面をそのままコピーして使っても大丈夫です。
書類全体で統一するためのミニ確認リスト
| 書類 | 表記が一致しているか確認するポイント |
|---|---|
| パスポート | 国籍・氏名・生年月日と整合しているか |
| 出生証明書 | 記載の市名と同じスペルか |
| 戸籍・翻訳書類 | ローマ字表記の統一 |
| 以前のビザ | 過去の申請データと一致しているか |
✅ すべて同じ「Tokyo」「Kyoto」「Sapporo」で統一されていれば安心。
書類ごとに「Tokyo-to」や「Tokyo city」と異なる書き方をしていると、照合で弾かれる場合があります。
迷ったときは「公式に問い合わせる」勇気を
ビザ関連は、少しでも不安があれば自己判断せずに問い合わせるのが一番安全です。
大使館やビザセンターの担当者は、こうした質問には慣れています。
短くても丁寧な英語で聞けば、きちんと答えてもらえます。
「質問するのは恥ずかしいこと」ではなく、
「確実に通すための最善の方法」と考えてOKです。
まとめ:提出前の最終チェック
最後にもう一度、出発前にこの5つを確認しておきましょう。
- 市名だけを英語で書いたか
- スペルミスがないか
- パスポートと一致しているか
- 旧市名や略称を使っていないか
- 公式基準(ヘボン式)で表記しているか
この5項目を確認するだけで、
「出生地の入力ミスによる再提出」はほぼ防げます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 出生地が「町」や「村」だった場合はどう書けばいいですか?
市ではなく町や村で生まれた場合でも、特別な英語は不要です。
正式名称をローマ字に直して書くだけで大丈夫です。
例:
- 三春町 → Miharu
- 白馬村 → Hakuba
「Town」や「Village」を付けても構いませんが、省略しても問題ありません。
例)Miharu Town / Hakuba Village どちらでも可です。
Q2. 出生地が合併されて、今は別の市になっています。どちらを使えばいいですか?
出生当時の地名で書いても問題ありません。
ただし、申請フォームに「Current name(現在の地名)」と書かれている場合は、
現行の市名を優先しましょう。
例:
「旧〇〇町(現〇〇市)」と備考欄に補足しておくと親切です。
City欄:Hashimoto
備考欄:Born in former Koyaguchi Town(旧高野口町に出生)
Q3. 英語表記はローマ字で書けばいいの?長音はどうするの?
はい、外務省のヘボン式ローマ字で表記します。
「ー」や「小さいゃゅょ」などは省略し、シンプルに書くのが基本です。
| 日本語 | 正しい表記 | よくある誤り |
|---|---|---|
| 東京 | Tokyo | Tōkyō, Tokyoo |
| 京都 | Kyoto | Kyouto |
| 札幌 | Sapporo | Sappro |
| 名古屋 | Nagoya | Nagoya City(City不要) |
ローマ字変換ソフトの結果は正確でないこともあるため、
公式の「ヘボン式一覧」を確認しておくと安心です。
Q4. 「City」欄に「Japan」を書いてもいいですか?
いいえ。
「Japan」は「Country of Birth」や「Nationality」欄に入力します。
「City」欄には市名だけを書きましょう。
× Tokyo, Japan
○ Tokyo
国名を重複して書くと、データベース上で“別の地名”として扱われることがあります。
Q5. 「City」のあとに「City」と書く必要はありますか?
不要です。
英語では、都市名のあとに「city」を付けなくても意味が通じます。
× Tokyo City
○ Tokyo
“City”はすでに項目名に含まれているため、繰り返すと冗長になります。
Q6. 出生地が外国の場合はどう書きますか?
外国で生まれた場合は、City欄に都市名、Country欄に国名を分けて書きます。
例:
City:Los Angeles
Country:United States
日本国籍であっても、生まれた国は「出生国」として記録されます。
「City」と「Country」は必ずセットで確認しましょう。
Q7. 自動入力で出てくる市名と違う場合、どちらを選ぶべき?
まずは、自動入力候補の中に正式な表記があるか確認します。
なければ「Other」や「Not listed」などを選び、備考欄で補足しましょう。
例:
“Born in Miharu Town, Japan(福島県三春町に出生)”
自分の市が見つからないときは焦らず、近隣の市や英語訳の候補を確認してみましょう。
Q8. 「City」欄を空欄のまま提出しても大丈夫?
基本的には空欄はNGです。
フォームが必須項目になっていれば、入力しないと送信できません。
わからない場合は「Unknown」や「Other」を選び、
備考欄で「City not listed(該当市が見つからない)」などと説明すればOKです。
Q9. パスポートに出生地が記載されていません。何を基準に書けばいい?
日本のパスポートには「出生地」が記載されていないため、
戸籍・出生届・母子手帳などの記録を参考にしましょう。
出生証明書がある場合は、そこに記載された市名を優先します。
「はっきり覚えていない」「戸籍の確認が難しい」場合は、
申請先に問い合わせて「推定で書いてよいか」を確認するのが安心です。
Q10. 書き方が間違っていたらどうなりますか?
すぐに拒否されることはありませんが、再提出や修正依頼が届く可能性があります。
軽微な誤字でも再確認になる場合があるため、送信前のチェックが大切です。
不安なときは送信前にスクリーンショットを撮っておくと、
修正指示が来た際にすぐ対応できます。
図解③:申請トラブルQ&A早見表(例)
| トラブル内容 | 原因 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 入力後にエラーが出る | 市名が候補にない | 「Other」を選び備考で補足 |
| CityとCountryが逆 | 入力欄の混同 | City=市名、Country=国名で修正 |
| スペルミス | 打ち間違い | 再入力または修正申請 |
| 旧市名のまま入力 | システム未登録 | 現行市名に修正、備考で補足 |
| 空欄のまま送信 | 必須項目の未入力 | 「Unknown」や「Other」を一時入力 |
最後に:FAQのまとめ
- 市名だけを英語で書くのが基本
- 旧市名も使えるが、現地名指定なら最新に合わせる
- 町・村でもローマ字でOK
- パスポートや戸籍と整合性を保つことが大切
迷ったときは「どんな書き方が一番“統一感”があるか」を基準にしましょう。
一貫性を守ることが、トラブルを避ける最大のポイントです。
まとめ|正確な記入でトラブルを防ごう
記入ルールの3つの基本をおさらい
ビザ申請の「place of birth city」は、たった一行の入力ですが、
審査においてはあなたを特定する重要な項目のひとつです。
正しく書くために、次の3つのポイントを覚えておきましょう。
① 市名だけを英語で書く
→ 都道府県名(Tokyo-toなど)や国名(Japan)は不要。
「City」欄には市の名前だけを入力します。
② 表記は外務省のヘボン式ローマ字で統一
→ 長音(ー)や「小さいゃゅょ」は省略してOK。
例:Tokyo/Kyoto/Fukuoka
③ パスポート・出生証明と一致させる
→ ビザ申請では複数のデータが照合されます。
過去の申請や戸籍上の表記とズレがないか、必ず確認しましょう。
よくある間違いを防ぐ3つのコツ
1. 「City」欄に“City”や“Japan”をつけない
→ “Tokyo city” “Tokyo, Japan” はNG。
英語では「Tokyo」だけで十分です。
2. 旧市名・略称を避ける
→ 「Hiro」や「Koyo」など地元の略称は使わず、
正式な市名で記入しましょう。
3. 一貫した表記で統一する
→ ビザ申請書、パスポート、出生証明など、
すべて同じ表記でそろえておくとトラブル防止になります。
トラブルを防ぐための“最終チェックリスト”
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 市名だけを書いている | “Tokyo city”“Japan”は書いていないか |
| スペル・大文字小文字が正しい | Osaka/Nagoya/Sapporo などを再確認 |
| 過去の書類と一致 | パスポート・出生証明と同じ表記か |
| 英語表記は公式基準 | ヘボン式ローマ字(例:Kyoto、Tokyo)に統一 |
| 旧市名・略称を使っていない | 現行の正式名を使用しているか |
この5項目を確認すれば、ほとんどの入力ミスを防げます。
特に“Japan”の重複と“旧市名のまま入力”は注意ポイントです。
公式サイトでの最終確認もおすすめ
記入ルールは国ごとに微妙な違いがあります。
申請前に、以下の公式ページを一度確認しておくと安心です。
参考にしたい信頼できる情報源
- 外務省「パスポートQ&A」
- 外務省「ヘボン式ローマ字表記一覧」
- 各国のビザセンター公式サイト(例:アメリカDS-160、カナダeTAなど)
- 大使館・領事館のFAQページ
国によっては「現在の市名で記入」と指定されている場合があります。
公式情報を優先し、不明点は問い合わせで確認しましょう。
不安なときは「シンプル&統一」を選ぶ
英語表記が難しく感じるときは、
シンプルに・短く・そろえる という3つのルールを意識しましょう。
- シンプルに → 市名だけ
- 短く → 長音や装飾を省く
- そろえる → すべての書類で同じ表記に
書き方に迷ったとき、「パスポートと同じにする」が一番確実です。
「Tokyo」「Osaka」「Kyoto」──このように短く、正確で統一された表記が理想的です。
最後に:正しい記入で安心して出発を
ビザ申請の手続きは、慣れない英語表記や細かい入力項目が多く、
最初は不安を感じる方も多いでしょう。
でも「出生地」は、いちばん落ち着いて対応できる項目です。
焦らず、一貫した書き方で丁寧に入力すれば問題ありません。
あなたの旅や留学のスタートがスムーズに進むよう、
このガイドが少しでもお役に立てればうれしいです。
記事のまとめ(要点おさらい)
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 基本ルール | 市名のみ英語で記入(都道府県・国名は不要) |
| 表記方法 | 外務省のヘボン式ローマ字で統一 |
| 注意点 | 旧市名・略称・“City”“Japan”の重複を避ける |
| トラブル回避 | 一貫した表記・スペル確認・公式情報の参照 |
| 最後の確認 | 提出前にチェックリストで最終確認 |